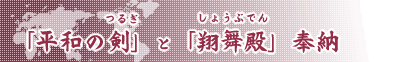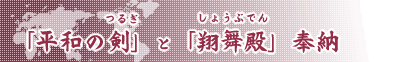| 1.図面製作 |
 |
初めに1/10の図面を書き、次に原寸大の拡大図を描く。
写真:「平和の剣」製作者 鴇田 力(トキタツトム)先生
■鴇田力先生履歴
重要無形文化財(人間国宝)故、香取正彦先生に師事、鋳金を学ぶ。同人間国宝、金森映井智師に彫金の技法を学ぶ。昭和30年頃より今日に至るまでに製作した作品中、梵鐘(ボンショウ)は百数余に及び、この「平和の剣」も含めて、世界的な作品も数点製作している。77歳の現在も尚、現場にて活躍している。 |
| 2.木型製作 |
 |
 |
「木型士」による
「平和の剣」の木型製作。
原寸図を見ながら彫刻し、木型を作り上げる。
 |
| 3.木型塗装 |
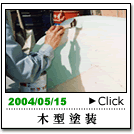 |
 |
出来上がった木型に表面を保護するための塗料を塗ります。
 |
| 4.鋳造「伝統的な焼型」 |
 |
「鋳物(イモノ)師」により鋳造された「平和の剣」
■焼型(ヤキガタ)という伝統的な鋳造方法にて製作
銅75%、錫(スズ)10%、亜鉛10%、鉛分5%
良質の唐金(カラガネ)にて「平和の剣」は製作されました。 |
| 5.仕上げ |
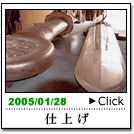 |
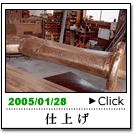 |
「仕上士」により
「平和の剣」の表面をできる限りきれいに磨き上げます。キズ、穴が開いていればそれを埋めます。
 |
| 6.色付け |
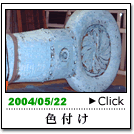 |
 |
「着色士」による色付け
酸の液を布に付けて、剣の表面を何度となくたたき、緑青を吹かせ、青い色が自然色になるまで仕上げをします。 |
| 7.漆仕上げ・完成 |
 |
「着色士」による漆(ウルシ)仕上げ」
緑青が自然色になり落ついたところで漆の原液を表面に拭い込みます。それにより銅合金本来の写真の様な非常に上品な青銅色となり「平和の剣」の完成となります。製作に要した時間は約半年間です。 |
 |
白鷺神社御神宝
「平和の剣」も完成。
年末〜1/末までの公開予定。
普段は目にすることができませんので是非、お参り下さい。 |